神社ギャラリー
神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。
※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。
神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

参道の社号標
足高神社・倉敷市
石造りの立派な社号標には式内(延喜式内社)であった事と、郷社であった事が刻まれている。

檜皮葺きの本殿
足高神社・倉敷市
式内小社で、旧社格は県社。祭神は大山津見命、配神は石長比賣命・木之花佐久夜比賣命。神階は正四位上。別名「帆下げの宮」。江戸時代後期までは「葦高神社」と表記されていた。倉敷市中心部の南部に位置する標高67メートルの足高山山上に鎮座する。現在は陸続きとなっているが、かつては「小竹島」または「笹島」と呼ばれる瀬戸内海(吉備の穴海)に浮かぶ島であった。他にも戸島、藤戸島、吉備の小島、奥津島などとも呼ばれていたという。
足高山は桃山時代から江戸時代前期の間に干拓され陸続きとなった。江戸時代を通じ岡山藩の支藩である鴨方藩の祈願所となり藩主が替わるたびに参拝した。現在、山上の神社周辺は足高公園となっており、春には桜の花見客で賑わう。

新年を待つ社殿
箆取神社・倉敷市
箆取神社は水島地域西部の連島町大平山の中腹にある神社である。
創建年代は不詳であるが、連島は奈良時代には都羅之郷と称し、壬生の乱の神官が神社から南に広がる瀬戸内海を眺めていた時、海面に 「箆」の神紋が顕れたことから箆取大権現と称したといわれている。江戸時代初期までは、連島は瀬戸内海に浮かぶ狐島で、都から九州の太宰府を結ぶ海路で重要な位置を占めていたことにより海にまつわる伝承が多い。また、宝暦の頃には連島の総鎮守として信仰集め、広い境内には長い回廊が左右に巡らされている。
周辺には桜、楓、ツツジが数百本植栽され、四季の変化が楽しめ、絵馬殿からの眺めは手前から西之浦の旧市街、水島市街と水島臨海工業地帯、遠方に水島灘と高梁川が臨める観光地となっている。なお、当社は崇敬神社につき氏子を持たない。

神輿渡御
厄神社・倉敷市
厄神社の秋祭りは、江戸時代の後期に、現在の倉敷市連島町西之浦へ本殿が移された際に、御神輿の巡行に御供をする千歳楽が作られたことに始まると言われています。
300年の歴史をもつ秋祭りでは、氏子町内の西町、奥、四丁内、腕の4つの支部からそれぞれ大若・小若と呼ばれる大小合わせて8基の千歳楽が繰り出し2日間で西之浦地区を15キロから20キロ曳行します。祭り初日は午後3時半に猿田毘古神社わきの串ノ山公園に8基の千歳楽が集結し、太鼓を叩き、伊勢音頭をアレンジした連島小唄を歌いながら力強く担ぎ上げ、秋祭りを盛り上げていました。

新年の参道
厄神社・倉敷市
厄神社のご祭神は神速須佐之男命で、記紀神話で出雲系神統の祖とされる神。伊弉諾・伊弉冉二尊の子。天照大神の弟。粗野な性格から天の石屋戸の事件を起こしたため根の国に追放されたが,途中,出雲国で八岐大蛇を退治して奇稲田姫を救い,大蛇の尾から天叢雲剣を得て天照大神に献じた。新羅に渡って金・銀・木材を持ち帰り,また植林を伝えたともいわれる。「出雲国風土記」では温和な農耕神とされる。

鈴緒
菅原神社・笠岡市
菅原神社の創建は延宝2年(1674)吉浜干拓地が完成したのを記念して、備後福山の藩主水野勝慶が造営されたといわれ、眼鏡橋は、明治20年に地元の石工が築いた。
写真は拝殿の鈴緒。

眼鏡橋とカキツバタ
菅原神社・笠岡市
菅原神社の眼鏡橋は岡山県の重要文化財に指定されている。また、境内の御手洗池では5月になると名物のカキツバタ2千本が開花する。

イチョウの神木
穴場神社・倉敷市
倉敷市の巨樹に指定されている穴場神社のイチョウ。
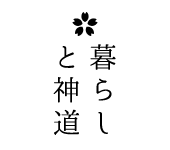
































秋祭りには千歳楽も参加する。