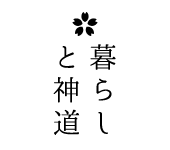神事の紹介
式年祭(式年御開帳祭)
瀧神社
708-1300 勝田郡奈義町滝本1973
- 祭礼日時
- 第37回式年御開帳祭は2026年4月
- 文化財指定
- 無
御開帳由緒:この岩屋山に鎮座まします大神は伊邪那美尊であって、諸神の大祖として万類の身を保ち、実入事は皆この大神のしからしむ所であって、此の大神の御神体は三十三年ごとに開扉開帳の式を一週間執り行い拝することができ、本殿に遷し奉る儀式が定例となっている(馬上の伊邪那美尊を刻みかえる)。この式には三種の宝器 すなわち鏡玉剣を揃えて開式するといういわれであり、このことは千数百年前から変わりがない。開帳すれば、年豊かに人安く開運・出世・富貴・繁盛・運命良長疑いなしといわれている。云々 瀧神社の前身である、神仏混合の瀧大領権の時代が長く続いた。この開帳行事は仏教色が強い。第1回御開帳は承和5年(838)に行われ、以来33年毎に執り行われてきた。平成5年に第36回御開帳が執り行われている。次回は2026年に第37回目が行われる。
神事の分類
神事の詳細
| 祭りの時間帯 |
|
|
| 祭りの対象 |
|
|
| 祭祀規程上の区分 |
|
|
| 祭りの趣旨・由来 |
|
|
| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |
|
| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |
|
|
| 祭典の参列者数 |
|
|
| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |
|
|
| 神職以外の祭りの奉仕者 |
|
|
| 神饌・供え物 | 品目 |
- |
| 供え方 |
- |
|
| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |
- |
|
| 競技・演武等の行事 |
- |
|
| 芸能 |
|
|
| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |
|
|
| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |
呼称 |
- |
| 形態 |
- |
|
| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |
- |
|
| 行列・社参・参列 | 形態 |
- |
| 一般の参列の可否 |
|
|
| その他の行事・所作 |
- |
|
祭りの時間帯
- 午前
- 終日(朝から夕刻・宵まで通して)
祭りの対象
- 本社(本殿)奉斎の祭神
祭祀規程上の区分
- 例祭以外の大祭
祭りの趣旨・由来
- 皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念する恒例の祭り
祭りの規模
祭典奉仕の神職数
- 2~5名
祭典奉仕の神職以外の祭員数
- 1~5名
祭典の参列者数
- それ以上の多数
祭礼行事の神職・祭員以外の所役
- 11~100名
神職以外の祭りの奉仕者
- 女性(未婚)
- 女性(既婚・老壮年)
- 幼児・児童(男女問わず)
- 男性(青少年)
- 男性(成年・老壮年)
- 老若男女さまざまな人々が多数参加
神饌・供え物
品目
-
供え方
-
芸術・文芸・物品奉納供進等の行事
-
競技・演武等の行事
-
芸能
- 能・狂言・歌舞伎・舞楽
こもり・禁忌・禊祓・神占などについて
- 水垢離・みそぎ
ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて
呼称
-
形態
-
神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御
-
行列・社参・参列
形態
-
一般の参列の可否
- 一般の方の参列・参加の希望があっても歓迎しない
その他の行事・所作
-