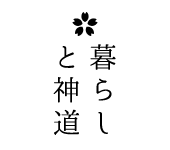神事について
各神事についてのご案内です。
1 |
年占い としうらない |
その年のよしあし、作柄や漁の豊凶、毎月の天候を占う神事など。 |
2 |
御奉射 おびしゃ |
年頭などに災厄を防除する意味の弓射の儀式など。 |
3 |
追儺 ついな |
悪鬼を祓い、疫病を除いて新年を迎える儀式など。 |
4 |
桃花祭・神能 とうかさい・しんのう |
中世、ご神前に桃花を供えたのが始まり。 |
5 |
夏越祓 なごしのはらえ |
無事夏を越すため、蘇民将来に由来する「茅の輪神事」など。 |
6 |
虫送祭 むしおくりさい |
稲作に害をもたらす虫を追い払う儀式など。 |
7 |
管絃祭 かんげんさい |
三管、三絃、三鼓の雅楽が奏される祭典など。 |
8 |
御鳥喰式 おとくいしき |
鎮座地選定に神鴉が先導した古事に由来するものなど。 |
9 |
おはけ おはけ |
オハケは神宿となる当屋の目印で、神の降臨を願って催した祭事など。 |
10 |
御注連おろし おしめのおろし |
当屋や御当田に竹を立て、注連縄をはって神霊を迎える祭事など。 |
11 |
宮座 みやざ |
氏子の中から輪番などで当屋を出して主宰する祭事など。 |
12 |
神楽 かぐら |
岡山県は神楽が盛んな地域。県内隈なく神楽があって種類も豊富。 |
13 |
神儀 じんぎ |
渡り拍子とも楽打ちともいい、歌詞を伴わない風流踊りなど。 |
14 |
太鼓踊 たいこおどり |
祭礼で奉納される太鼓を用いた踊りなど。 |
15 |
神殿入 こうどなり |
祭礼の宵祭に行われる灯明行列など。 |
16 |
火祭 ひまつり |
大火や灯火、松明の火で、神を招く目印や浄化などの意味を持つ祭典など。 |
17 |
だんじり だんじり |
山車(だし)とも呼ばれ、御神霊の「依りまし」として練り歩く祭典など。 |
18 |
獅子舞 ししまい |
霊獣である獅子が悪霊を圧服させるという信仰に由来する舞踊など。 |
19 |
湯立 ゆだて |
浄祓や卜占のため、釜の熱湯を笹でふりかける儀礼など。 |
20 |
流鏑馬 やぶさめ |
馬を馳せながら弓で的を射る神事で、年占いの意味を持つ神事など。 |
21 |
神輿行事 みこしぎょうじ |
神輿は神霊を奉安する輿。御神幸など。 |
22 |
国恩祭 こくおんさい |
皇祚の無窮、国家の繁栄、郡内平穏を祈る祭事など。 |
23 |
無言の神事 むごんのしんじ |
一切無言で行われる祭典など。 |
24 |
若宮祭 わかみやまつり |
浄化し神として祀られた祖霊の慰霊祭など。 |
25 |
競漕 きょうそう |
船を漕ぐ速さを競い、その勝敗によって吉凶を占う年占の一種。 |
26 |
競馬 けいば |
馬の資質を競い合い、早駆けなどの行事を神に奉納するものなど。 |
27 |
玉取 たまとり |
玉を取り合ったり替え合ったりして、その年の福男女を決める神事など。 |
28 |
綱引 つなひき |
綱を引き合って力を競い合う神事など。本来は作物などの豊凶を占う神事。 |
29 |
相撲・角力 すもう |
農作物の豊凶を占う農耕儀礼の神事など。 |
30 |
神明祭 しんめいさい |
鬼火焚きや左義長などとも呼ばれ、小正月の火祭りの一種。 |
31 |
鳴釜 なるかま |
神前の釜で熱湯を沸かし、釜鳴りの音の大きさや長さで吉凶を占う。 |
32 |
御田植 おたうえ |
早乙女や代掻き牛が出て、囃しや田植歌に合わせて苗を植える神事など。 |
33 |
焼石 やきいし |
焼いた石を床面に投げ、砕け具合によって吉凶を占う神事など。 |
34 |
五穀納め ごこくおさめ |
五穀を供えて祈念する神事など。 |
35 |
餅つき もちつき |
年中行事等の節目につかれるものなど。 |
36 |
雨乞い あまごい |
〈祈雨〉干ばつ時等に行われ、祀る神は村々の氏神の他、竜神等雨天神が多い。 |
37 |
田の実 たのみ |
稲の初穂を田の神・氏神などに供える穂掛けの神事など。 |
38 |
式年祭 しきねんさい |
決まった年ごとに行われる祭祀のこと。 |
39 |
潟祭 かたまつり |
岡山名産の牡蠣の養殖において、豊穣を願う神事。 |
40 |
日待祭 ひまちさい |
特定の日に人々が籠って一晩明かす祭り。 |
41 |
夏祭 なつまつり |
御霊信仰や厄神信仰に関わることが多い。 |
42 |
社日 しゃじつ・しゃにち |
春分・秋分に最も近い戌の日に、土地神を祭る。 |
99 |
その他 |
福迎え、牛神祭り、えびす祭り、会陽、雛流し、亥の子、御供、ご膳据、など |