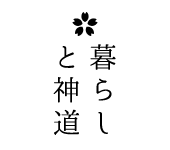神事の紹介
神楽
八門神社
719-2643 新見市土橋1803
- 祭礼日時
- 13年に一度
- 文化財指定
- 無
長作神楽といわれ、昔追っ手にに追われていた「長作」の居場所を追っ手に告げた者達がおり、その為に長作は捕まり殺された。その後この事に関与した者達に次々と災いが降り懸かった為、長作の魂を鎮める為にお堂を建てお祀りし、13年に1度「長作神楽」という蛇神楽を行うようになった。関係ある者達が集まり、藁で蛇を作り当屋の家で荒神神楽を夜通し行う。明朝は藁で作った蛇を皆でかついで田畑を練り歩き、最後に長作堂の脇にある木に納めて祭りを終える。
神事の分類
神事の詳細
| 祭りの時間帯 |
|
|
| 祭りの対象 |
|
|
| 祭祀規程上の区分 |
|
|
| 祭りの趣旨・由来 |
|
|
| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |
|
| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |
|
|
| 祭典の参列者数 |
|
|
| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |
|
|
| 神職以外の祭りの奉仕者 |
|
|
| 神饌・供え物 | 品目 |
- |
| 供え方 |
- |
|
| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |
|
|
| 競技・演武等の行事 |
- |
|
| 芸能 |
|
|
| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |
|
|
| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |
呼称 |
|
| 形態 |
|
|
| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |
- |
|
| 行列・社参・参列 | 形態 |
- |
| 一般の参列の可否 |
- |
|
| その他の行事・所作 |
- |
|
祭りの時間帯
- 終日(朝から夕刻・宵まで通して)
- 徹夜(夕刻・宵から朝まで)
- 昼夜を通して
- 数日間
祭りの対象
- 祖霊・英霊・その他諸々の神霊(慰霊祭・祖霊祭・祖霊社祭・忠魂碑・顕彰碑・供養碑や墓前の祭りなど、大祓・遥拝もこれに含む)
祭祀規程上の区分
- その他の諸祭(特に規程による区分のされない祭りを含む
祭りの趣旨・由来
- 農耕に関わる由緒や伝承がある祭り(御田植祭など)
- 歴史上の事件や人物に由来する祭り
- 講社の祭り(組合等団体の祭り)
祭りの規模
祭典奉仕の神職数
- 1名
祭典奉仕の神職以外の祭員数
- 11名以上
祭典の参列者数
- 50名前後まで
祭礼行事の神職・祭員以外の所役
- 11~100名
神職以外の祭りの奉仕者
- 伶人(神職が伶人を務める場合を含む)*伶人とは、雅楽をおこなうもの
- 神役・頭屋(その他、この類の奉仕者を含む)
- 特定の家系の者(例:奉仕の所役の家系が定まっている場合)
- 特定のグループ(例:組、集団、講、神事・神楽・芸能等の保存会、氏子青年会、神輿保存会・同好会、敬神婦人会など)
- 老若男女さまざまな人々が多数参加
神饌・供え物
品目
-
供え方
-
芸術・文芸・物品奉納供進等の行事
- 工芸品・その他の物品の奉納・展覧・供進・品評会
競技・演武等の行事
-
芸能
- 神楽(奉納芸能・神賑行事としての専門演奏家等による神楽。里神楽)
こもり・禁忌・禊祓・神占などについて
- 湯立て
- 託宣・神託(粥占・筒粥、年占行事などを含む)
ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて
呼称
- その他の名称で呼ばれる
形態
- 車はなく、かついで移動する
- 大きな人形・動物形・魚形などのつくりもの(ヘリポテ・ヤゴロウドン・牛鬼・ネブタの類)
神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御
-
行列・社参・参列
形態
-
一般の参列の可否
-
その他の行事・所作
-